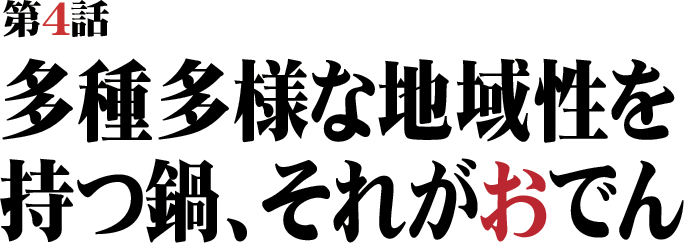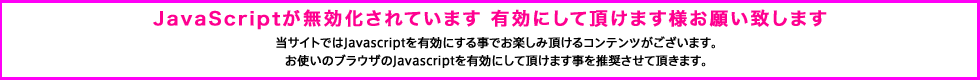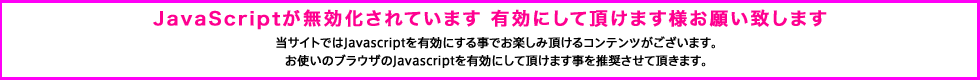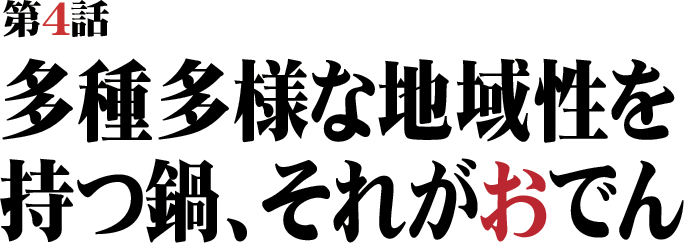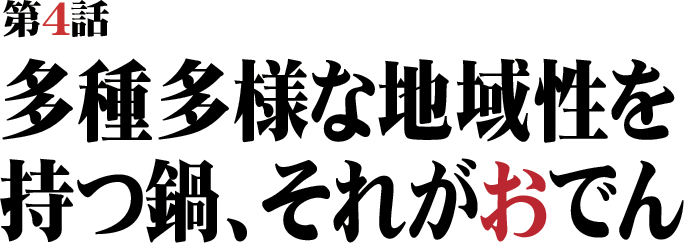

火付け役はマスコミ。意外と知らないニッポンの味?
B級グルメが注目を集めている。ブームの裏には、バブル経済の破綻して早20年経つが、高級グルメは高嶺の花のまま、懐に優しいリーズナブルな価格帯が消費者に支持されているという理由がある。そして、もうひとつは理由として考えられるのが、テレビ番組や雑誌などで、地域ならではの食習慣や食文化が紹介されるようになったからだろう。県民性の違いを面白おかしく紹介する番組や、それをクイズにした番組、グルメを中心とした旅番組など、紹介の手法も多岐に渡っている。
また、流通やインターネットの発達、さらに、真空調理やレトルト技術の進歩といったふたつの要素によって、様々なグルメの“お取り寄せ"が可能となり、わざわざ、その土地やその店に行かなくても、テレビや雑誌で見たグルメを家庭で簡単に楽しめるようになったという背景がある。当たり前のものには、もう飽きてしまった消費者は、今まで知らなかった手の届くグルメを求めているようだ。
鍋というジャンルで考えると、その地域差がある鍋の筆頭が、おでんである。コンビニエンスストアでのおでんの販売をきっかけに、おでんは全国で画一化されつつあるように思われるが、実は、コンビニエンスストアのおでんも、地域によって異なるダシや具材で構成されているそう。その多用性、地域性は他の鍋に類をみない。
手軽さゆえに、地域ならでは特徴が生まれた
そもそも、おでんの歴史は古く、発祥は室町時代に串に刺した豆腐のみそ焼きに始まるといわれている。今で言う、田楽だ。その後、様々な具材を煮込む今のおでんが登場したのは江戸時代頃。身近な素材をダシで煮込むだけという料理法のおでんは、またたく間に全国各地に伝播していった。そのため、ダシだけではなく、煮込む具材にも地域性がある。また、夕食だけではなく、手軽なファストフードとして、駄菓子などでも売られていたため、子供のおやつとしても伝播していきやすかったと考えられている。
おでん文化は、それぞれの地域で独自に開化していったのだ。
ちなみに、2006年に実施されたあるアンケート調査では「冬に食べたい鍋料理」の第一位はダントツで、おでん。続いて、すき焼き、寄せ鍋、しゃぶしゃぶと続く。ポイントは「冬」というところにあるようで、すき焼きやしゃぶしゃぶは、ご馳走として冬だけでなく、年間を通じて食卓に登場する機会があるが、おでんは「体が温まる食べ物」として、冬のイメージがとても強く、また、家庭で食べる鍋として定着している。
おでんの中で、人気がある具材は、全国的にみて、大根と玉子が圧倒的だ。あるアンケートでは3位のこんにゃくにかなりの差をつけている。面白いのは、4位以降には各地において、地域性が見られる具材が登場する。
また、おでんにつける薬味としては、全国的には、練り和からしが主流だが、この薬味についても地域性が存在している。
さらに、海外にもおでんは存在する。韓国では「おでん」という名前そのものが使われており、日本から伝わったものらしい。中国ではコンビニおでんが大ヒット。チベットにもおでんに類似するものがある。
地域のおでん エトセトラ。
それでは、全国各地のおでんをみていこう。
まずは、ダシについてだが、全国的に昆布を入れるのが前提だ。東日本では魚介ダシが好まれる。関西・中国には牛すじ、九州では鶏がらから、ダシをとる。
【ダシの地域性】
- 北海道→カツオ、利尻昆布、いわし節
- 東北・信越→カツオ、利尻昆布、煮干、宗田節
- 関東→カツオ、利尻昆布
- 東海→カツオ、利尻昆布、むろ節
- 関西・中国→カツオ、真昆布、牛だし
- 九州→カツオ、利尻昆布、鶏がら
具材には、共通するものもいくつかある。
【具材の共通性】
■全国共通の具材
大根、玉子、こんにゃく、もち巾着、ごぼ天、ちくわ
北海道おでん・・・海産物の具材+生姜味噌
北海道産昆布を用いた、薄い醤油味。海産物の豊富な地域性ゆえに、一般的な具材の他に、昆布やカニ、ツブ貝などが入っている。また、和からし以外に、生姜味噌をつけて食べる。
青森おでん・・・青森おでんの会がB-1グランプリに出店(2005年)
ツブ貝、ネマガリタケ、大角天(さつま揚げの一種)が入り、串に刺さっているのが特長。甘辛い生姜味噌や柚子味噌をつけて食べる。味噌は津軽味噌を使う。
 関東風おでん(ちくわぶ・揚げボール・つみれ)
関東風おでん(ちくわぶ・揚げボール・つみれ)
ふわふわのはんぺん、小麦粉を練ったちくわぶが必ず入る。関西でのはんぺんと呼ばれるものは、平天、または丸天と呼び、区別しているのが特長。さらに、ボールといわれる丸くて小さい練り物や、つみれなど、練り物を多く入れて、ダシに深みを出している。
静岡おでん・・・名物黒はんぺんがスペシャル具材
濃い口醤油を使った色の濃いダシが特徴。焼津名物である黒はんぺんが具材として入る。串に刺された具の上に、だし粉と呼ばれるイワシの削り節や、鰹節、青海苔をかけて食す。焼津では、なるとも定番の具材で、さらに、鰹のへそと呼ばれる鰹の心臓を串に刺していれることも。2007年には静岡おでんの会がB-1グランプリ第3位に―。
飯田おでん(長野)・・・ネギダレを愛用
一般的なおでんを各自の皿にとってから、たっぷりの長ねぎのみじん切りと削り節、醤油を合わせたタレをかけて食べる。からしを使う人はほとんどいない。
富山おでん・・・昆布消費量日本一。おぼろ昆布をかける
一般的なおでんを各自の皿にとってから、白とろろ昆布をかけて食べるのが特徴。具材には珍しい練りものも多い。白エビ入りつみれやすす竹、あんばやし(薄切りこんにゃく)など。
名古屋おでん・・・八丁味噌で色濃く仕上げる
愛知県名産の八丁味噌で甘く仕上げたダシを使う。豚バラや豚すじ、豚もつなど豚肉が入ることもある。シメには玉子をご飯にのせ、煮汁をかけたぶっかけごはんを楽しむ。
大阪おでん(関東煮)・・・牛スジ&クジラでコクのある味
牛スジを串に刺した具材は必須で、他にもねぎ袋という、薄揚げの中に青ネギを入れたものなどオリジナルな具材がある。タコの足が入っているのも特徴的だ。 また、今は高級食材となってしまったクジラは、以前は庶民の味と親しまれ、おでんには必要不可欠な食材だった。特に、コロと呼ばれる皮と、さえずりと呼ばれる舌が具材としては重宝され、旨味のあるダシがでる。
姫路おでん・・・生姜醤油であっさりと
あっさりと煮たおでんを皿にとり、たっぷりの生姜醤油で食すのが特長。刻んだ青ネギを散らすこともある。
松江おでん・・・おでん屋数、全国1位
県庁所在地の中で、最もおでん屋が多いとされ、2010年にはおでんフェスティバルを開催。ただし、共通される特徴はあまりない。
香川おでん・・・うどん屋にはおでんが必須
一年を通じて、おでんが食べられている。うどん屋のサイドメニューとしては必須アイテムで、必ずといっていいほど、セルフサービス式のおでんがある。
熊本おでん・・・馬のすじ肉「馬すじ」は定番
コクのあるダシがでると、熊本では定番の具材が、馬のすじ肉。
沖縄おでん・・・トンコツ風味のコクのある味
豚足をメインとしたダシで、具材に季節の葉物野菜が加わる。また、豚足は具材としても食べられる。他にソーキなどが入ることもある。
旅行に行った際には、ぜひ各地のおでんを楽しんでみてほしい。また、具材は地元でしか手に入らないものもあるが、生姜醤油やネギダレなど、家庭で簡単に作れるものもあるので、試してみてはいかがだろうか。地域おでんと共に、旅行気分も味わえるのでは?!
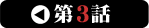
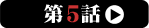
|