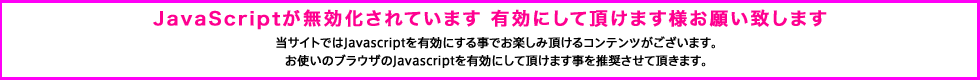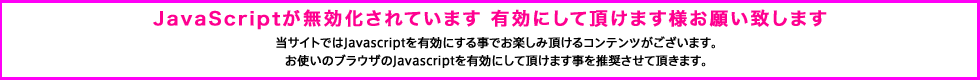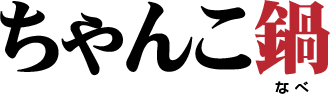
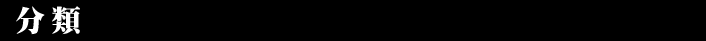
だし:鶏ガラスープ、昆布だし、かつおだし、薄口・濃口醤油、酒、みりん、味噌など
つけだれ:ポン酢醤油など
シメ:雑炊、うどん、中華麺など
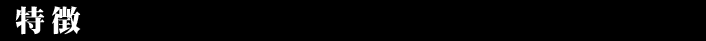
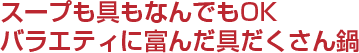
ちゃんこ鍋には決まりがなく、寄せ鍋風、ちり鍋風、水炊き風、チゲ風などどんな鍋もその範疇に含まれるとされている。
鶏ガラ、トンコツ、カツオだしなど多種多用なだしでたくさんの具を煮込むことは共通している。
味付けは塩、醤油、みりん、味噌などに加え、キムチや唐辛子、カレー味などにすることもある。ちり鍋風ならポン酢醤油をつけて食べるが、たくさんの具の旨みがしみ出ただしごと食べることが多い。
具材は鶏、豚、牛などの精肉はぶつ切りやスライス、つくねを作るなどして加える。魚介はイワシ、タラ、エビ、ハマグリなど旬のものを用い、切り身やつくねにして入れる。かつては四つん這いになることを連想させる四つ足の動物は避けられていたが現在では豚、牛肉はもちろんソーセージなども入る。相撲部屋のちゃんこ鍋は、縁起を担ぐ意味もあり、肉類は未だ鶏だけのようだ。
野菜はハクサイ、ニラ、ネギ、キャベツ、モヤシ、ゴボウ、ニンジン、タマネギなどさまざま。さらに、はるさめ、豆腐、うす揚げ、しらたき、巾着、キノコ類など。とにかくたくさんの具をおいしいスープとともにいただく鍋だ。シメはごはんやうどん、中華麺を入れるがこれもさまざまである。
ルールがない鍋なので、家庭で作る具だくさん鍋をちゃんこ鍋ということもある。また、ちゃんこ鍋店は、相撲の大阪場所など大きな興行が行われる地域だけでなく、全国各地に数多くあり、人気がある鍋料理となっている。
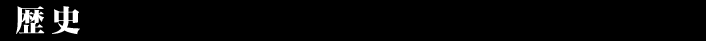

「ちゃんこ」とは力士の食事や、力士が食事をすることを指す。
その語源には、いくつかの説がある。
- 中国から長崎に伝わった「チャンクォ鍋」を長崎に巡業に来た力士が知り、その調理法を取り入れたという説。(ちなみにチャンクォとは大きな鉄の鍋の意)
- 相撲部屋の料理番のおやじを「ちゃん」と呼んだところから生まれたという説
他にも諸説ある。(1)と(2)のどちらの説か有力かは意見の分かれるところだが、力士の食べる食事をちゃんこと呼び、力士が食べる鍋料理を「ちゃんこ鍋」と呼ぶようになった。
相撲部屋で食べられているちゃんこ鍋は、差し入れられた野菜や魚など、その日その日にある材料を鍋にぶちこんで水やだしで煮て食べる。特に鶏ガラでとっただしは「そっぷ炊き」とよばれ、ポン酢醤油などのつけだれは使わずに食べる。また、力士の体づくりに必要なタンパク質に富む鶏肉や魚などを多く入れるのも特徴だ。
元力士やその親族、相撲界出身者などが各地にちゃんこ鍋専門店を作ったことで、各相撲部屋秘伝の鍋料理が広く一般にも食べられるようになった。大阪では創業40年を越える老舗店もある。
飲食店で提供されるちゃんこ鍋は、店ごとに秘伝のだしがあり、加える具材もシンプルなものからエビやカニなどが入る豪華なものまでさまざま。自家製のつくねや具材の下処理など専門店ならではの手の込んだ鍋料理となっている。
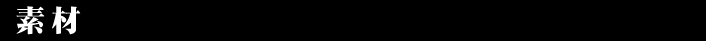 <主な具材>
<主な具材>
★肉(鶏、豚、牛など)
★魚貝(イワシ、タラ、ハマグリなど)
キャベツ、ニラ、タマネギ、ネギ、モヤシ、ゴボウ、キムチ、豆腐、キノコ類、はるさめなど
シメ:雑炊、うどん、中華麺など
<だし>
鶏ガラスープ、かつおだし、薄口・濃口醤油、酒、みりん、味噌、コチュジャン、ニンニク、唐辛子など
<つけだれ・薬味>
すりごま、ポン酢醤油、生卵など
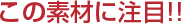
ミンチやすり身を使ったつくねを加えるのもオススメ。魚はぜひ旬のものを使いたい。
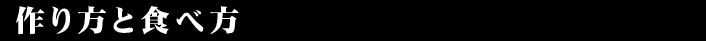
・材料は適当な大きさに切る、下ゆでするなど食べやすいように下処理をする
・ベースのスープに好みの調味料を加えて味を調える
・だし、すべての具材を鍋に盛り加熱する
・煮えた具からだしごと一緒に食べる
・シメはごはん、うどん、中華麺などを加える

・あらかじめ、たっぷりのすり白ごまをだしに加えておくとコクが出る
・スープによってつけだれをそえる |