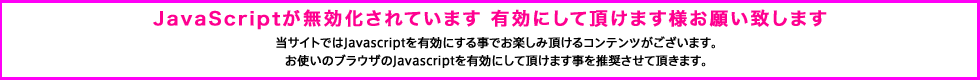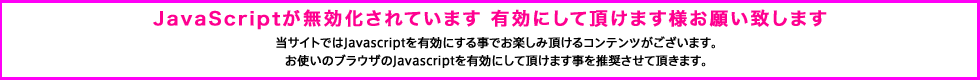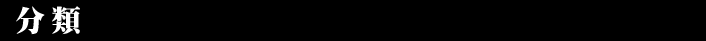
だし:昆布だし、白味噌、赤味噌、しょうが、酒、みりん
つけだれ:なし
シメ:雑炊
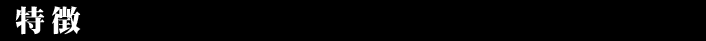

真冬に旬を迎えるカキは広島や三重で養殖が盛んに行われており、大阪などへ出荷されている。英語のスペルで「R」の付かない5〜8月のカキは食べるなといわれ、旬の時期のみ営業をする専門店もあるほど。鳥取などで穫れる岩ガキは夏が旬だが、希少で高価なため土手鍋で食べられることはない。
白味噌と赤味噌を5:1程度の割合でよく練り合わせたものをだしに溶かしながら、カキやハクサイ、白ネギなどの具材を煮る。現在はだしに味噌を溶いた状態で具材を煮ていく食べ方が多いが、かつては鍋の内側面に味噌を壁のように塗りつけて作ることが多かった。側面に塗った味噌の上に野菜をならべ、さらにその上にカキをのせる。野菜からでる水分で味噌を溶かしながら、煮えたカキを煮汁につけて食べる。煮詰まりすぎたら、昆布だしを足して水分を調節する。味噌を直接鍋に塗る方法では焦げ付きやすく、土鍋よりも鉄鍋が適しているようだ。味噌にはカキ特有の臭みを和らげる効果があり、さらにおろしショウガをたっぷりと加えてもよい。
カキ料理専門店ではシメにカキの炊き込みご飯を提供することが多い。味噌がたっぷりと入った残り汁はかなり濃厚なので、雑炊にするよりも昆布だしなどで炊きあげた炊き込みご飯のほうが食べやすいのかもしれない。
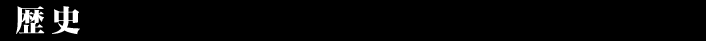

江戸時代の大阪には、大川筋や道頓堀川など多くの川筋に蠣船(かきぶね)がとどまりカキ料理を提供していた。その船を初めて大阪に出したのが、広島の小西屋五郎八という人物だ。
カキ養殖の歴史は古く、江戸時代にはすでに盛んに行われていた。カキを養殖していた小西屋五郎八が販路を求めて大阪にやってきたのが蠣船(かきぶね)の始まりといわれている。その後、しばらく途絶えることもあったが、元禄年間(1700年頃)に仁右衛門が再び大阪に売り込みにやってきた。そして、宝永5年(1708年)に大阪に起こった大火の際、仁右衛門が高麗橋の高札(こうさつ)※を火から守ったことから功績を認められ、市内のどの橋畔でもカキ販売を許可されるようになった。
当初は生のカキをそのまま販売し、カキの身を殻からはずすところを実演して見せていた。その後、さまざまなカキ料理とともに提供された土手鍋が人気を博したという。カキの本家本元ともいえる広島の食べ方が本場さながらに大阪へ輸入されたのだ。
土手鍋の由来には、
1.味噌を土手のように盛るから
2.大阪でカキ料理屋を始めた土手長吉という人が考案したから
3.大盛況の蠣船に入りきれなかった客が周囲の土手で食べたから
などさまざまな説がある。
※高札・・・人が多く行き交うところに目立つように建てられた掲示板。一般的な法律が書かれており、重要なものとされていた。
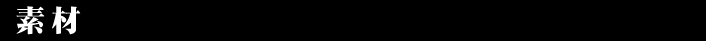
<主な具材>
カキ 、ハクサイ、白ネギ、シュンギク、焼き豆腐、シイタケ、ゴボウ
シメ:雑炊、うどん
<だし>
昆布だし、白味噌、赤味噌、酒、みりん
<つけだれ>
なし
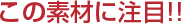
土手鍋に使うカキは12~2月頃に旬を迎える。
この時期には餌となるプランクトンが多く発生しカキの栄養が充実するためだ。
「花見を過ぎたらカキを食べるな」ということわざもある。
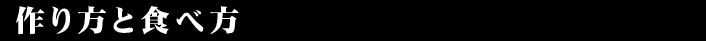
・カキは薄い塩水かダイコンおろしで丁寧に洗い、臭みをとっておく
・野菜などの具材は適当な大きさに切る
・白味噌と赤味噌を合わせて練り、昆布だしで固さを調整する
・鍋の内側面に練り味噌をまんべんなく塗りつける
・練り味噌の上にハクサイなど水分がよく出る野菜を並べ、さらにカキをのせる
・野菜の水分が出てきたら、側面の味噌を溶かしこみながら味を調整し、たまった汁に具をつけながら食べる
・シメはごはん又はうどんを加えて煮る

・カキは丁寧に洗うとくさみがやわらぐ
・だしに練り味噌を完全に溶いてから具材を煮てもよい |