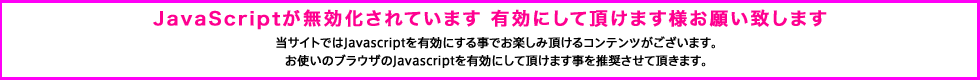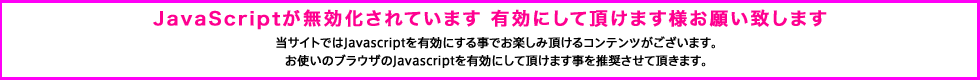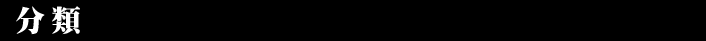
だし:昆布
つけだれ:ポン酢、ごまダレ
シメ:雑炊
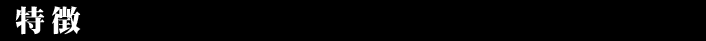
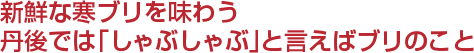
薄切りにしたブリを昆布だしにさっと通し、霜降り状態になったところをポン酢醤油やゴマダレをつけて食す。濃厚なブリの旨みに、さっぱりとしたポン酢醤油やゴマダレがよく合う。
旬は12〜2月頃の真冬。旬の寒ブリは身の色も美しく、はりがあり、脂がのっている。しゃぶしゃぶにするなら鮮度の高い天然ものがよいが、丹後地方では良質な養殖ものも手に入る。
飲食店や旅館などでは、造りよりも薄く切った身を花が咲いたように美しく大皿に盛った物が出る。その他の具材は、白菜、白ネギ、シュンギク、豆腐などさまざま。脂が乗ったブリと相性がよいのは白ネギで、斜め薄切りにして、水にさらしたものをたくさん用意することもある。シメは雑炊。
旬を迎えると、丹後地方だけでなく関西では、しゃぶしゃぶ用のブリの切り身が魚売り場に並ぶ。飲食店のコース料理や旅館ではブリの握り、あら炊きなどと、ブリづくしの料理と共に提供されることもある。
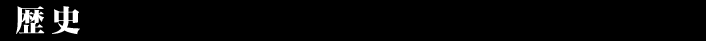
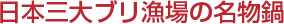
京都府の日本海側、丹後半島に位置する伊根町の沖合は、ブリの日本三大漁場一つに数えられている。伊値湾沿いには1階が舟のガレージ、2階が住居になった独特の舟屋と呼ばれる家屋が建ち並び、その景観もよく知られる。
12〜1月にもっとも美味しい時期を迎える寒ブリは、伊根を始め宮津など丹後エリア各地でとれる。
照り焼き、煮物、刺身が定番だったブリ料理にブリしゃぶが誕生したのはそれほど昔ではない。昭和53年に宮津の旅館組合が新名物を作る目的で考案されたといわれている。その後、関西地方や全国にも広まっていった。旬の時期には遠方からもはるばるブリしゃぶを求めて訪れる人も多い。
関西では、わかな→つばす→はまち→めじろ→ぶり、と名を変えて成長する出世魚として正月料理にもかかせないブリ。
そのブリを使ったしゃぶしゃぶなので「出世鍋」という別名を持つ。
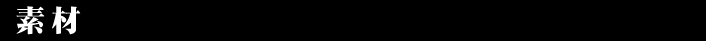 <主な具材>
<主な具材>
★ブリ
白ネギ、白菜、シュンギク、豆腐
シメ:ごはん、卵、ネギ
<だし>
昆布
<つけだれ>
ポン酢醤油・ゴマダレ
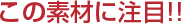
色が美しく、ハリがある新鮮なブリを選ぼう
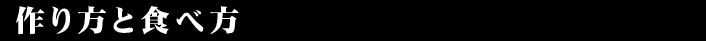
・鍋に水と昆布を入れゆっくりと煮立たせる
・ブリを加えてさっと煮る
・野菜やそのほかの具材を煮る
・ポン酢醤油やゴマダレで食す
・シメは、ごはんを加えて雑炊に

・ブリは表面の色が変われば食べ頃。火を通しすぎないように。 |